専門卒の公務員の年収はどのくらい?【職種別・年代別で解説】
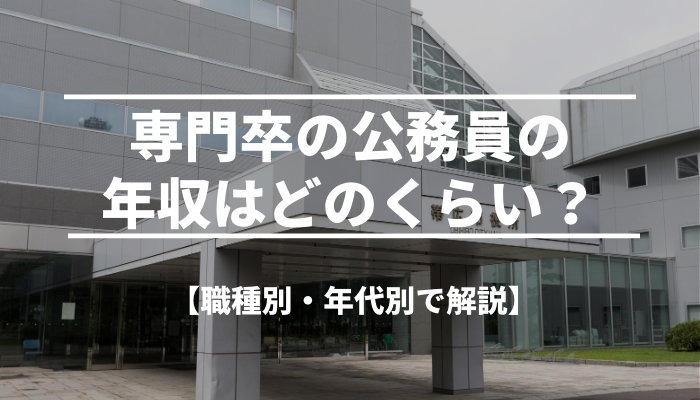
「専門卒で公務員になった場合、年収はどのくらいなのか?」「大卒と比べて収入に差はあるのか?」と気になっていませんか。公務員は安定した職業ですが、給与の伸びやキャリアの進め方に不安を感じる人も多いでしょう。
本記事では、専門卒公務員の年収を 職種別・年代別に詳しく解説 し、 昇給や昇進の仕組み、年収アップの方法、副業の可能性 まで掘り下げて紹介します。また、公務員を辞めた後のキャリアや転職先、独立の可能性についても解説するため、将来の選択肢を広げるヒントが得られます。
この記事を読むことで、公務員としての 具体的な年収の推移やキャリアプランが明確になり、自分にとって最適な働き方を考える材料 を得られます。専門卒でも公務員として安定した収入を確保し、将来のキャリアを築く方法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
専門卒で公務員になったら年収はどれくらい?

専門卒で公務員になった場合、どのくらいの年収が得られるのか気になるところです。ここでは、初任給から生涯賃金、学歴による年収差、ボーナスや退職金の実態、民間企業との比較について詳しく解説します。
専門卒公務員の平均年収【初任給~生涯賃金まで】
専門卒公務員の平均年収は、初任給から徐々に上昇し、安定した収入が期待できます。例えば、地方公務員の初任給は月額18万円前後であり、年収換算すると約250万~300万円になります。年齢を重ねるごとに昇給し、30代で400万円台、40代で500万円以上、50代では600万円台に到達するケースが多いです。
この安定した収入は、公務員特有の昇給制度によるものです。公務員は勤続年数に応じた定期昇給があるため、景気の影響を受けにくく、将来の収入が見通しやすい点が特徴です。また、生涯賃金では約2億円前後とされ、同じ学歴の民間企業勤めよりも安定した収入を得られる可能性が高いといえます。
しかし、公務員の給与は年功序列のため、若い間の収入は控えめです。そのため、若年層のうちに収入を増やすには、資格取得や昇進を目指すことが重要です。長期的に安定した収入を求める人には、公務員の給与体系は適しているといえるでしょう。
専門卒と大卒・高卒の年収の違い【どれくらい差がある?】
公務員の給与は学歴によって異なり、専門卒と大卒、高卒では一定の差が生じます。専門卒の初任給は約18万円前後ですが、大卒は20万円以上となり、年間で約20~30万円の違いがあります。高卒の場合、初任給は16万円前後となるため、専門卒との差はそれほど大きくありません。
この差は、昇進スピードや昇給幅にも影響します。大卒公務員は専門卒よりも昇進の機会が多く、管理職に就く可能性が高いため、40代以降の年収差が大きくなります。一方、高卒と専門卒の違いは昇進スピードよりも基本給の違いにあり、勤続年数が長くなるほど専門卒の方が優遇される傾向があります。
ただし、専門卒でも資格を取得したり、試験を受けたりすることで、大卒と同等の昇進ルートに進める可能性があります。学歴による給与差はあるものの、実績や努力次第で年収を高めることは十分可能です。
専門卒公務員のボーナス・退職金はいくら?
公務員のボーナスは年間4.4~4.5カ月分が支給されるため、基本給の高い人ほどボーナス額も増えます。例えば、専門卒公務員の20代の年収が350万円の場合、ボーナスは約80~100万円程度となります。30代では約120万円、40代では150万円以上が支給されることが一般的です。
退職金については、勤続年数によって異なりますが、平均して2000万円前後が支給されるケースが多いです。例えば、地方公務員として定年まで勤め上げた場合、退職金の平均額は2200万円前後となります。国家公務員も同様の水準ですが、役職によって増減することがあります。
ボーナスと退職金の安定性は、公務員の魅力の一つです。民間企業では業績によって変動することがありますが、公務員は法律で定められているため、大きく変動することはほとんどありません。長期的な資産形成を考える上でも、安定したボーナスと退職金が得られることは、公務員の大きなメリットといえます。
公務員と民間企業の年収比較【どちらが良い?】
公務員と民間企業の年収を比較すると、初任給や若いうちは民間企業の方が高くなる傾向があります。特に、営業職や技術職などの職種では、成果に応じたインセンティブが加わるため、30代で500万円以上の年収を得るケースも珍しくありません。一方、公務員は年功序列の昇給制度のため、若年層のうちは民間と比べると低めの収入になります。
しかし、40代以降になると、公務員の年収は安定的に増え、民間企業の平均と同等かそれ以上になることが多いです。特に、リストラのリスクがなく、退職金や年金が手厚いため、トータルで見ると公務員の方が有利な面もあります。また、福利厚生や労働時間の安定性を考慮すると、ライフワークバランスを重視する人にとっては公務員の方が適しているといえます。
最終的に、公務員と民間企業のどちらが良いかは、求める働き方によって異なります。短期間で高収入を目指すなら民間企業の方が向いていますが、長期的な安定を求めるなら公務員の方が適しているでしょう。
専門卒公務員の年収【職種別】

専門卒で公務員になる場合、職種によって年収に大きな違いがあります。行政職や技術職、特殊な職務を担う公務員など、それぞれの年収水準を知ることで、将来的なキャリアプランを明確にできます。ここでは、市役所や県庁職員、警察官や自衛官、国家公務員、専門職公務員、学校職員や図書館司書の年収について詳しく解説します。
地方公務員(市役所・県庁職員)
地方公務員の年収は、自治体の規模や財政状況によって異なりますが、一般的な市役所や県庁職員の初任給は18万~20万円程度です。年収は20代で300万円前後、30代で400万円台、40代で500万円以上となるケースが多いです。
公務員の昇給は毎年一定額が加算される仕組みで、40代以降になると安定した高収入が得られます。特に、管理職に昇進すれば年収700万円以上を目指すことも可能です。ただし、大都市の自治体ほど給与水準が高く、地方の小規模自治体では若干低めになる傾向があります。
給与の安定性や福利厚生の充実度は魅力的ですが、民間企業のような大幅な昇給は期待しにくいため、給与の伸びを考慮して昇進や資格取得を目指すことが重要です。
警察官・消防士・自衛官
警察官や消防士、自衛官は、専門卒でも採用される職種であり、一般的な地方公務員よりも給与水準が高い傾向があります。警察官の初任給は約22万円で、30代で500万円、40代で600万円を超えることも珍しくありません。消防士も同様に、危険手当や夜勤手当が加わるため、一般の行政職よりも高収入となるケースが多いです。
自衛官は、一般隊員として採用されると初任給が18万円前後ですが、階級が上がるにつれて給与も増加します。例えば、3曹に昇進すると年収400万円以上、1曹以上になると500万円を超えることが一般的です。また、住宅手当や扶養手当が充実しており、福利厚生の面でも優遇されています。
これらの職種は、体力的な負担が大きいものの、手当が充実しているため、安定した収入を得られます。ただし、職務の特性上、リスクを伴う業務が多いため、適性を考慮して選択することが重要です。
国家公務員(税務職・裁判所職員など)
国家公務員の年収は、地方公務員と比較して若干高めに設定されている傾向があります。例えば、税務職員や裁判所職員の初任給は19万~21万円で、30代で450万円以上、40代で550万円を超えることが一般的です。
税務職員は、国税庁に所属し、税務調査や納税指導を行う職種であり、手当が充実しているため、地方公務員と比べても収入面で有利です。裁判所職員は、書記官や事務官として勤務し、安定した収入と労働環境が魅力です。
また、国家公務員は全国転勤があるため、地方公務員よりも勤務環境が変わりやすい特徴があります。そのため、勤務地の変動を許容できる人にとっては、収入面やキャリアの成長を考慮すると魅力的な選択肢になります。
専門職公務員(技術職・医療職など)の年収
専門職公務員は、技術職や医療職など、特定の分野に特化した職種です。例えば、土木技術職や建築技術職の初任給は20万円前後で、30代で500万円台、40代で600万円以上になることが一般的です。
医療職では、保健師や診療放射線技師などの職種があり、これらの専門職は地方公務員の中でも特に給与水準が高い傾向があります。例えば、保健師の初任給は22万円前後で、30代で500万円、40代で600万円以上となるケースが多いです。
専門職公務員は、資格取得が必須であり、専門知識が求められますが、その分給与水準が高く、長期的に安定した収入を得やすい職種といえます。資格を活かしたい人や専門的なスキルを生かして働きたい人にとって、魅力的な選択肢になります。
学校職員・図書館司書などの公的機関職員
学校職員や図書館司書は、公務員の中でも比較的給与が低めの職種です。例えば、学校事務職員の初任給は18万円前後で、30代で350万円、40代で450万円程度になります。図書館司書も同様に、給与水準は低めですが、安定した雇用が魅力です。
一方で、教育機関に関わる仕事のため、福利厚生が充実している点がメリットです。また、勤務時間が安定しているため、ワークライフバランスを重視する人にとっては働きやすい環境といえます。
ただし、昇給の幅は他の公務員と比べて小さいため、収入面での向上を目指す場合は、資格取得やキャリアアップの方法を検討することが求められます。
専門卒公務員の年収【年代別】

専門卒公務員の年収は、年代によって大きく変化します。勤続年数に応じた昇給があるため、長く勤務するほど収入は安定して増えていきます。ここでは、20代から50代までの年収推移と、定年後の待遇について詳しく解説します。
20代の年収
20代の専門卒公務員の年収は、比較的控えめですが、安定した昇給が見込めます。例えば、地方公務員の初任給は約18万〜20万円であり、年間の総支給額は約250万~300万円程度です。
この収入は、同じ学歴の民間企業勤務者と大きな差はありませんが、ボーナスが支給される点が公務員の強みです。20代後半になると、昇給により基本給が増え、年収は350万〜400万円程度に達します。ただし、昇進の機会が少ないため、大幅な給与アップは期待しにくい傾向があります。
20代で収入を増やすためには、資格を取得して手当を得る、または早期の昇進を目指すことが重要です。
30代の年収
30代になると、専門卒公務員の年収は大きく伸び、安定した生活を送れる水準になります。一般的な地方公務員の年収は、30代前半で400万円前後、30代後半では450万円〜500万円程度に達します。
この年代では、主任や係長といった役職が付き始めるため、昇進による給与アップの可能性も高まります。また、住宅手当や扶養手当が加算されることで、実際の可処分所得が増える点も公務員のメリットです。
一方で、民間企業の同世代と比べると、業種によっては公務員の年収が見劣りするケースもあります。特に営業職や専門技術職の分野では、成果に応じた高収入を得る人も多いため、収入面での差が広がることがあります。
公務員として30代で年収を向上させるには、試験に合格して上級職に昇格するか、専門分野のスキルを磨いてキャリアアップを図ることが効果的です。
40代の年収
40代になると、公務員の年収は500万円以上となり、安定した収入を確保できます。地方公務員の年収は、40代前半で500万〜550万円、40代後半では600万円を超えることも珍しくありません。
この年代では、課長補佐や課長といった管理職に昇進する人も増えます。役職に就くと、基本給の上昇に加えて管理職手当も支給されるため、収入の伸びが加速します。また、勤続年数が長くなることで、退職金の積み立ても着実に増えていきます。
ただし、公務員の給与体系は年功序列であるため、民間企業の管理職と比較すると収入の増加スピードは緩やかです。民間企業の管理職が700万円以上を得るケースと比べると、公務員の収入は控えめといえます。
この年代では、より上位の管理職を目指すか、専門資格を活かして手当を増やすことで、収入の最大化を図ることが重要になります。
50代の年収と定年後の待遇
50代になると、公務員の年収は最も高くなり、管理職としての責任も大きくなります。50代前半の年収は600万円〜700万円、50代後半では700万円を超えるケースもあります。特に、部長職や局長クラスに昇進した場合、年収800万円以上に達することもあります。
定年は原則として60歳ですが、定年後も再任用制度を活用することで、公務員として働き続けることが可能です。再任用後の給与は現役時代よりも減少するものの、年金受給開始までの生活費を補う役割を果たします。また、退職金は勤続年数に応じて支給され、地方公務員であれば2000万〜2200万円程度が支給されるのが一般的です。
公務員の定年後の生活は、民間企業と比べても安定しているため、退職後も経済的な不安が少ない点が大きなメリットです。老後の生活を見据えた資産形成を行うことで、より安心してリタイア後の生活を送ることができます。
専門卒公務員のキャリアと働き方

専門卒公務員のキャリアは、昇給・昇進の仕組みや異動・転勤の有無によって大きく左右されます。公務員の給与体系は年功序列を基本としながらも、昇進の機会を活かせば年収を増やすことが可能です。ここでは、昇給や昇進の仕組み、専門卒が管理職になれるのか、職種ごとの異動や転勤の実態について解説します。
公務員の昇給・昇進の仕組み
公務員の昇給は、毎年一定額が加算される「定期昇給」と、昇進によって給与が増える「昇格昇給」の2つの要素で成り立っています。定期昇給は年1回実施され、基本給に数千円から1万円程度が加算される仕組みです。この制度により、勤続年数が長くなるほど安定的に年収が上昇します。
一方、昇進は試験や勤務評価によって決まるため、積極的にキャリアアップを目指すことが重要です。例えば、主任や係長に昇格すると、基本給に加えて役職手当が支給され、年収が一気に増加します。ただし、公務員の昇進には一定の年数が必要であり、早期の昇格を望む場合は、実績を積むことや資格取得が求められます。
民間企業と比較すると昇給のスピードは緩やかですが、景気に左右されずに安定した給与が確保できる点が公務員の強みです。昇進のチャンスを活かすことで、より高い収入を目指すことが可能です。
専門卒で管理職になれる?キャリアの天井は?
専門卒公務員でも管理職への昇進は可能ですが、大卒と比較すると昇進のハードルがやや高くなります。公務員の昇進は、学歴だけで決まるわけではなく、勤務評価や試験の結果が大きく影響します。しかし、実際には大卒の方が管理職候補として優遇されるケースが多いため、専門卒が高いポジションに就くには相応の努力が必要です。
例えば、地方公務員の場合、専門卒でも係長や課長補佐までは比較的昇進しやすい傾向にあります。しかし、課長や部長以上のポストになると、大卒の候補者が優先されることが一般的です。そのため、専門卒が高い役職を目指すには、昇進試験で高評価を得ることや、専門分野でのスキルを磨くことが不可欠です。
公務員のキャリアは学歴だけで決まるわけではなく、実績や意欲が重要になります。専門卒でも適切な準備をすれば、管理職への道は開かれています。
異動や転勤の有無【職種ごとの違い】
公務員の異動や転勤の有無は、職種や勤務先によって大きく異なります。地方公務員の場合、基本的には同じ自治体内で異動が行われ、勤務地が大きく変わることは少ないです。例えば、市役所職員であれば、市内の異動が中心であり、県庁職員なら県内のさまざまな部署へ配置換えされることが一般的です。
一方、国家公務員は全国転勤の可能性があるため、異動の頻度が高く、勤務地の変動が大きい特徴があります。例えば、税務署勤務の職員は数年ごとに異動があり、全国の税務署へ転勤する可能性があります。警察官や消防士、自衛官も職種によっては転勤の可能性があり、特に幹部候補生の場合は、全国の拠点を経験することが求められます。
異動や転勤の有無は、公務員の働き方に大きく影響します。地元で長く働きたい場合は、地方公務員を選ぶのが適しており、キャリアアップのために広範囲で経験を積みたい場合は、国家公務員の選択肢を検討するのが良いでしょう。
専門卒公務員のメリット・デメリット

専門卒公務員には、安定した収入や充実した福利厚生といったメリットがある一方で、給与の伸びが遅い、異動が多いといったデメリットも存在します。ここでは、公務員として働く際に知っておくべきメリット・デメリットについて詳しく解説します。
メリット1.安定した給与と福利厚生
公務員の最大の魅力は、安定した給与と手厚い福利厚生が保証されていることです。景気の影響を受けにくく、毎年一定の昇給があるため、長期的に収入の見通しが立てやすい点が特徴です。
また、医療費の補助や住宅手当などの福利厚生も充実しており、家族がいる場合でも生活の安定が図れます。特に、共済組合を通じた健康保険は、民間企業の社会保険よりも自己負担が少なく、公務員ならではの強みといえます。
民間企業では業績によって給与が変動することがありますが、公務員は法律に基づいて給与が決まるため、突然の収入減少のリスクが低い点も大きなメリットです。
メリット2.景気に左右されない職業
公務員は、民間企業と異なり、景気の影響をほとんど受けません。例えば、不況時に民間企業がリストラを実施することがある一方で、公務員は解雇のリスクが極めて低いです。
さらに、公務員の給与は国や自治体の予算で運営されているため、景気悪化に伴う給与カットが起こりにくい特徴があります。実際に、過去の経済不況時でも、公務員の給与は大きな影響を受けずに維持されてきました。
この安定性は、長期的なキャリアを考える上で非常に重要です。特に、家庭を持つ人やローンを組む際には、公務員の安定した収入が大きな強みになります。
メリット3.ワークライフバランスが取りやすい
公務員は、民間企業と比べて労働時間が管理されており、残業が少ない傾向にあります。特に、地方公務員の場合、定時退社がしやすく、プライベートの時間を確保しやすい点が魅力です。
また、有給休暇の取得率が高いことも特徴の一つです。公務員は計画的な休暇取得が推奨されており、家族や趣味の時間を大切にしながら働くことが可能です。
一方で、繁忙期には業務が増えることもありますが、民間企業のような極端な長時間労働は発生しにくいため、安定した生活リズムを維持しやすい職業といえます。
メリット4.退職金・年金制度が充実
公務員は、退職金や年金制度が手厚く、老後の生活が安定しやすい点も大きな魅力です。例えば、地方公務員の退職金は平均2000万円以上とされており、民間企業の平均を上回ることが多いです。
また、共済年金制度が整っており、老後の年金額も比較的高めに設定されています。特に、長年勤務した場合、支給額が安定するため、定年後の生活資金の不安が少なくなります。
これらの制度によって、公務員は現役時代だけでなく、退職後の生活まで安定が確保されている点が強みといえます。
デメリット1.給与の伸びが遅い
公務員は毎年の昇給があるものの、給与の伸びが緩やかである点がデメリットです。特に若いうちは、民間企業の同年代と比べて年収が低くなるケースが多いです。
民間企業では成果に応じた昇給やボーナスの増額が期待できますが、公務員は一律の給与体系に基づいているため、短期間で大幅な収入アップは難しくなります。
そのため、早く高収入を得たい場合は、公務員よりも民間企業のほうが向いている可能性があります。公務員として年収を増やすには、昇進や資格取得による手当の増加を狙うことが重要になります。
デメリット2.年功序列の文化
公務員の給与や昇進は、年功序列が基本となっており、実力主義の民間企業とは異なります。優れた成果を上げても、昇進のタイミングが決まっているため、すぐに給与に反映されることは少ないです。
また、上司や先輩との関係性が重要視される職場文化があり、実力だけで評価されにくい点もデメリットです。特に、若手職員が新しいアイデアを提案しても、組織のルールに縛られて採用されにくい場面が多くあります。
このような環境に不満を感じる場合、公務員よりも民間企業のほうが向いている可能性があります。ただし、安定した昇進制度があるため、長期的に見ると着実にキャリアアップができる点は公務員の強みといえます。
デメリット3.異動や転勤がある場合が多い
公務員は、異動や転勤の可能性が高い職業です。地方公務員の場合、同じ自治体内での異動が数年ごとに行われることが一般的です。特に、市役所や県庁の職員は、さまざまな部署を経験することが求められます。
国家公務員の場合、全国転勤の可能性があり、特に幹部候補の職員は頻繁な異動を経験します。家庭を持っている場合、転勤による生活環境の変化が負担になることがあります。
異動を前向きに捉えられる人には、幅広い業務経験を積む機会となりますが、特定の分野で長く働きたい人にとっては、デメリットとなる可能性があります。
デメリット4.民間と比べて副業が制限される
公務員は、民間企業と異なり、副業が法律で制限されています。例えば、一般的な企業では投資やフリーランスの仕事を並行して行うことが可能ですが、公務員は原則として本業以外の収入を得ることが禁止されています。
近年、一部の自治体では副業解禁の動きもありますが、現状では厳しい制約があるため、収入を増やす手段が限られています。そのため、給与以外の収入源を持ちたい場合、公務員の職務は選択肢として適していない可能性があります。
一方で、安定した給与が確保されているため、副業をしなくても十分な生活を維持できる点は公務員の強みといえます。長期的な収入を重視するか、短期間での収入増を重視するかによって、向き不向きが分かれる職業です。
専門卒公務員の年収を上げる方法

専門卒公務員は、年功序列の昇給制度があるため、勤続年数が増えるほど安定的に収入が上がります。しかし、大幅な年収アップを目指す場合は、昇進や資格取得、副業の可能性を探ることが重要です。ここでは、公務員が年収を上げる具体的な方法について解説します。
昇給・昇進で年収アップする仕組み
公務員の年収を増やす最も確実な方法は、昇給と昇進の制度を活用することです。公務員の昇給には「定期昇給」と「昇格昇給」があり、それぞれ異なる仕組みで給与が上がります。
定期昇給は、毎年決まった時期に基本給が数千円から1万円程度増額される制度です。年功序列のため、特別な努力をしなくても安定的に給与が増えていきます。ただし、増加幅が小さいため、大きな年収アップにはつながりにくいです。
一方、昇進による昇格昇給は、役職が上がることで給与が大幅に増加する仕組みです。例えば、係長や課長補佐に昇進すると、基本給に加えて役職手当が支給され、年収が一気に増えます。特に、管理職に昇進すると年収700万円以上を目指せるケースもあります。
公務員として早期に年収を上げたい場合、昇進試験に合格することが重要です。試験勉強や実績を積むことで、キャリアアップのチャンスを広げられます。
資格取得で手当を増やす方法
公務員は、特定の資格を取得することで手当が支給される場合があります。資格手当は、職種によって異なりますが、毎月の給与に加算されるため、継続的な収入アップにつながります。
例えば、地方公務員の技術職では、土木施工管理技士や建築士の資格を取得すると、資格手当が支給される自治体があります。また、消防士が救急救命士の資格を取得すると、手当が上乗せされるケースもあります。
さらに、行政職の公務員が社会保険労務士やファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得すると、昇進時の評価が高くなり、キャリアアップにつながる可能性があります。資格取得は、直接的な手当だけでなく、昇進の後押しとなる点もメリットです。
公務員として効率的に年収を増やすには、自身の職種に関連する資格を取得し、手当を増やすことが有効な戦略といえます。
公務員の副業は可能?【収入を増やす方法】
公務員は法律によって副業が厳しく制限されています。国家公務員法や地方公務員法では、原則として営利目的の副業が禁止されており、違反すると懲戒処分の対象となる可能性があります。
しかし、例外的に認められるケースもあります。例えば、不動産収入や株式投資は、一定の条件を満たせば問題ありません。また、自治体によっては、講師活動や執筆業などの一部の副業が許可される場合もあります。近年では、地域活性化に貢献する活動など、公益性の高い副業に限り認められるケースが増えています。
公務員が収入を増やすためには、副業ではなく、昇進や資格取得による収入アップを目指すことが現実的な方法といえます。どうしても副業を検討したい場合は、事前に勤務先へ確認し、適切な手続きを踏むことが必要です。
公務員を辞めた後のキャリア・年収の変化

公務員としてのキャリアを積んだ後、転職や独立を考える人も少なくありません。公務員から民間企業へ転職した場合、年収はどのように変化するのか、どの業界へ転職しやすいのかを知ることは重要です。また、独立や起業を目指す場合の可能性についても解説します。
公務員から民間企業に転職すると年収は上がる?下がる?
公務員から民間企業へ転職すると、年収は職種や企業の規模によって変動します。一般的に、転職直後の年収は下がる傾向があります。なぜなら、公務員時代の給与は年功序列で安定しており、転職先の企業では即戦力としての評価が求められるため、スタート時の給与は控えめになることが多いからです。
一方で、スキルや経験を活かせる業界へ転職すれば、年収が上がる可能性もあります。例えば、自治体の財務や法務に関わっていた公務員が、コンサルティング会社や企業の管理部門に転職するケースでは、年収500万円以上を得ることも可能です。また、専門資格を持っている場合は、転職後にキャリアアップしやすく、結果的に年収が上昇することもあります。
公務員の給与は安定していますが、大幅な昇給は期待しにくいため、民間企業で成果を出すことで、将来的に年収を上げる道も選択肢となります。
公務員から転職しやすい職種・業界
公務員から民間企業へ転職する場合、これまでの経験を活かせる職種を選ぶことが成功のカギとなります。特に、行政や財務、企画関連の業務に従事していた人は、企業の総務・人事・経理部門への転職が比較的スムーズです。
また、法律や契約に関する業務を担当していた場合は、企業の法務部門やコンサルティング業界でも需要があります。特に、行政書士や社会保険労務士などの資格を取得している場合は、専門性を活かした転職がしやすくなります。
さらに、警察官や消防士などの経験を持つ人は、警備会社や危機管理関連の業界への転職がしやすいです。教育分野では、地方自治体で教育関連の業務を担当していた人が、学校法人や研修機関での仕事に転職するケースもあります。
転職を考える際は、公務員時代に培ったスキルや専門知識を活かせる業界を選ぶことで、スムーズなキャリアチェンジが可能になります。
退職後の独立・起業は可能?
公務員から独立・起業することは可能ですが、成功するためには十分な準備が必要です。公務員時代は副業が禁止されているため、独立に向けた実務経験を積む機会が限られていることが課題となります。そのため、独立を考える場合は、事前に必要なスキルを習得し、業界の動向を把握しておくことが重要です。
独立しやすい分野としては、行政書士や社会保険労務士などの資格を活かした事務所開業、コンサルティング業務、教育・研修業などが挙げられます。特に、元公務員としての信頼性があるため、行政手続きや人事労務関連のビジネスでは顧客を獲得しやすい傾向があります。
また、不動産投資やフランチャイズ経営といったビジネスも、公務員退職後に取り組む人が増えています。これらの事業は、安定した収入があった公務員時代に資金を準備しておくことで、スムーズにスタートしやすくなります。
独立・起業を成功させるには、公務員時代に培ったスキルを活かしつつ、早めの準備を進めることが重要です。リスクを抑えながら計画的に進めることで、安定した事業運営が可能になります。
専門卒で公務員を目指すためのポイント

専門卒で公務員を目指すには、試験対策や面接準備が欠かせません。公務員試験の難易度や合格率を把握し、専門学校・短大卒が有利になる試験科目を理解することで、効率的に合格を目指せます。また、面接や論文対策も重要な要素となるため、具体的な準備方法について詳しく解説します。
公務員試験の難易度と合格率
公務員試験の難易度は、受験する職種や自治体によって異なります。一般的に、地方公務員試験は倍率が5〜10倍程度、国家公務員試験(一般職)は10倍以上になることが多いです。特に、人気のある自治体や職種では競争が激しく、より高い点数が求められます。
試験内容は、「教養試験」「専門試験」「面接試験」の3つが基本となります。専門卒向けの試験では、専門科目が課されないケースも多く、基礎的な学力と面接対策が合否のカギを握ります。例えば、市役所の行政職は教養試験が中心となるため、数的処理や文章理解の対策を徹底することが重要です。
合格率は、試験の種類や受験者数によって変動しますが、一般的に地方公務員試験の最終合格率は20〜30%程度です。難易度が高い試験ほど、計画的な学習が求められるため、早めの準備が合格の確率を高めるポイントとなります。
専門学校・短大卒で有利になる試験科目は?
専門学校や短大を卒業した受験者が有利になる試験科目は、実務に直結する分野が多いです。例えば、法律系の学科を卒業している場合、地方公務員試験の「法律分野」で優位に立てます。また、経理・会計系の学科を修了していれば、財務・経理関連の職種で専門知識を活かせるため、試験や採用後の業務でも強みになります。
技術職の公務員試験では、建築・土木・電気といった分野が出題されるため、該当する専門学科を修了していると、知識面でのアドバンテージを得られます。さらに、医療・福祉系の学科では、保健師や社会福祉士などの資格を活かして公務員として働ける道が開かれています。
試験対策として、専門学校で学んだ知識を活かすだけでなく、出題範囲を分析し、重点的に学習することが重要です。専門性を活かせる職種を選択することで、合格の可能性を高めることができます。
面接・論文対策のポイント
公務員試験では、筆記試験の得点だけでなく、面接や論文の評価も最終的な合否に大きく影響します。特に、面接試験は人物評価が重視されるため、しっかりとした準備が必要です。
面接では、「公務員を志望する理由」「自治体や職種に対する理解」「これまでの経験をどう活かせるか」などが問われます。回答の際は、具体的なエピソードを交えながら、論理的に伝えることが重要です。例えば、学生時代に培ったスキルや経験を公務員としてどのように活かすかを明確に説明できると、評価が高まります。
論文試験では、社会問題や政策に関するテーマが出題されることが多いため、日頃から時事問題に関心を持ち、文章構成の練習をしておくことが必要です。PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識し、論理的に文章を組み立てることで、説得力のある論文を書けるようになります。
面接や論文は、一朝一夕で対策できるものではありません。事前に模擬面接を受ける、論文の添削を受けるなどの準備を進めることで、合格に向けた万全の対策を整えられます。
専門卒公務員のリアルな声・体験談

専門卒で公務員として働く人が、実際にどのような年収を得ているのか、どのような働き方ややりがいを感じているのかを知ることは、将来のキャリア選択に役立ちます。また、公務員になって良かった点や後悔した点を把握することで、仕事の現実を理解しやすくなります。ここでは、実際の年収実態、働き方の特徴、仕事の満足度について詳しく解説します。
実際に働いている専門卒公務員の年収実態
専門卒の公務員は、初任給が18万〜20万円程度で、年収はおおよそ250万〜300万円からスタートします。その後、定期昇給や手当の増加によって30代では400万円台、40代で500万円以上に到達するケースが多くなります。
公務員の年収は職種によっても異なります。例えば、地方公務員の行政職では、30代で年収450万円前後、40代では500万円を超えることが一般的です。一方、警察官や消防士、自衛官のような危険手当が加算される職種では、20代のうちから400万円を超えることもあります。
公務員の給与は民間企業のように急激に上昇することはありませんが、安定した昇給制度があるため、長く勤めるほど収入の増加が期待できます。そのため、着実に年収を上げたい人にとっては、専門卒公務員の給与体系は大きなメリットといえます。
専門卒公務員の働き方・やりがい
専門卒の公務員は、定時勤務が基本であり、比較的ワークライフバランスが取りやすい働き方が特徴です。業務内容は所属する部署によって異なりますが、行政サービスの運営や住民対応、インフラ管理など、多くの人の生活に直接関わる仕事を担います。
公務員のやりがいは、社会貢献の実感を得られる点にあります。例えば、市役所職員であれば、地域の福祉や防災、教育支援など、住民の生活向上に貢献できる機会が多くあります。また、警察官や消防士は、人命を守る責任のある仕事であり、その達成感は大きなものになります。
一方で、仕事の成果が短期間で目に見えにくい点や、業務がルーチン化しやすい点が課題と感じる人もいます。しかし、長期的に見れば、地域社会の発展に貢献している実感を得られるため、安定した環境で働きながら社会貢献をしたい人にとっては適した職業です。
公務員になって後悔したこと・良かったこと
公務員になって良かったと感じる点として、多くの人が挙げるのは「安定した収入」と「ワークライフバランスの良さ」です。特に、リストラのリスクがほぼないことや、福利厚生が充実している点は、大きな魅力となっています。また、年次ごとの昇給が保証されているため、長期的な生活設計が立てやすい点もメリットです。
一方で、公務員になって後悔する人の多くは、「給与の伸びが遅い」「柔軟な働き方がしにくい」「年功序列の文化が強い」といった点を挙げています。特に、成果を出しても給与に即反映されない点は、民間企業と比較して物足りなさを感じる部分かもしれません。また、組織のルールが厳格であり、変化の少ない環境が合わないと感じる人もいます。
結局のところ、公務員としての働き方が向いているかどうかは、個人の価値観によります。安定した環境で長く働きたい人にとっては最適な職業ですが、スピード感のあるキャリアアップを求める人には不向きな側面もあります。事前に公務員の実態を理解し、自身のライフプランに合った選択をすることが重要です。
まとめ
専門卒で公務員を目指す場合、安定した収入や福利厚生、ワークライフバランスの良さが大きな魅力となります。初任給は控えめですが、年功序列の昇給制度により、長期的に安定した年収が得られます。一方で、給与の伸びが緩やかであり、成果がすぐに評価されにくい点はデメリットといえます。
キャリアアップを目指すなら、昇進試験の受験や資格取得が重要になります。公務員試験の難易度は自治体や職種によって異なりますが、計画的な学習と面接対策を行うことで合格の可能性を高められます。また、転職や独立を視野に入れる場合は、専門知識を活かせる分野を選ぶことが成功のカギとなります。
公務員は、安定性を求める人にとっては非常に魅力的な職業です。自身のキャリアプランに合わせて、公務員としての働き方を選択し、最適なキャリア形成を目指しましょう。
