専門学校の就職率の真実とは?数字のカラクリと就職に強い学校の選び方
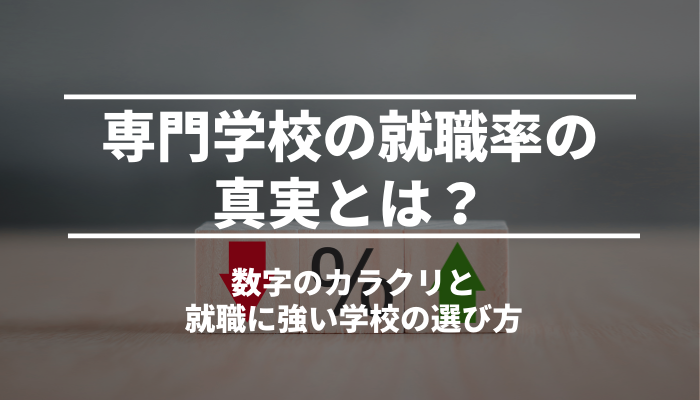
専門学校の就職率が高いと言われていますが、その数字の意味を正しく理解できていますか?
「就職率100%と書かれているけど、本当に希望の職に就けるのだろうか」「専門学校と大学では就職の有利・不利があるのか知りたい」といった疑問を持つ人も多いでしょう。
本記事では、専門学校の就職率のカラクリや業界別の実態、就職に強い学校の見極め方を詳しく解説します。
この記事を読むことで、就職率の数字に惑わされず、本当に自分のキャリアに役立つ情報を見極める力が身につきます。さらに、就職を成功させるために今から何をすべきかが明確になるため、卒業後の進路に自信を持てるようになります。
ぜひ最後まで読んで、納得のいくキャリア選択をしてください。
1. 専門学校の就職率は本当に高い?その数字を鵜呑みにしてはいけない理由

専門学校の就職率は90%以上と高い数値が示されています。しかし、その数字だけを見て安心するのは危険です。なぜなら、計算方法や定義によって、実態とは異なる見え方をすることがあるからです。ここでは、就職率の計算方法の違いや「就職率100%」の意味について詳しく解説します。
1-1. 就職率の計算方法:卒業生全体と就職希望者ベースではここまで差が出る
専門学校の就職率は、「卒業生全体に対する就職者の割合」と「就職希望者に対する就職者の割合」の2通りの計算方法があります。多くの専門学校が公表している就職率は後者を基にしており、進学者や就職を希望しなかった人を分母から除外しています。そのため、実際の就職率は学校が発表している数字より低い可能性があります。
例えば、ある専門学校の卒業生が100人いたとして、そのうち60人が就職し、20人が進学、20人がその他の進路を選んだとします。この場合、卒業生全体を分母とした就職率は60%ですが、就職希望者(60人+20人=80人)を分母とすると就職率は75%になります。こうした違いがあるため、専門学校の就職率を見る際は計算方法を確認することが大切です。
1-2. 「就職率100%」は嘘ではないが、その数字が示さないもの
一部の専門学校では「就職率100%」と強調していますが、それが必ずしも全員が希望の職種や正社員として就職できたことを意味するわけではありません。多くの学校では、契約社員やアルバイトなども就職としてカウントしている場合があります。さらに、学校側が就職率を維持するために、学生に短期間の仕事を紹介し、一時的にでも雇用関係を結ばせるケースもあります。
また、「就職希望しない」と申告した学生は就職率の計算から外れるため、見かけ上の就職率が上がることもあります。こうした背景を知らないと、「この学校に行けば確実に正社員として就職できる」と誤解する可能性があるでしょう。専門学校の就職率を確認する際は、「どのような就職が含まれているのか」をしっかり調べることが重要です。
2. 専門学校卒業後の就職実態と大学卒との比較

専門学校の就職率は高いと言われますが、大学卒と比べてどのような違いがあるのでしょうか。就職先の種類や選択肢、内定獲得のタイミング、学歴による影響などを詳しく解説します。専門学校と大学、それぞれの強みと課題を理解し、自分に合った進路を選ぶための判断材料にしてください。
2-1. 公式データに見る専門学校の就職率:平均は○○%前後、その裏にある実情
文部科学省の調査によると、専門学校の就職率は90%以上と高い水準を維持しています。しかし、その数値には注意が必要です。専門学校の就職率は「就職希望者に対する就職者の割合」で計算されるため、進学者や就職を希望しない人は分母に含まれていません。この点を理解していないと、実際よりも就職しやすいと錯覚してしまう可能性があります。
さらに、就職した人のすべてが正社員とは限りません。契約社員やアルバイト、派遣社員なども就職者にカウントされる場合があるため、数字だけを見て判断するのは危険です。就職率の高さだけでなく、どのような企業・職種に就職できているのかを確認することが重要になります。
2-2. 専門学校vs大学:就職率に大差はないが就職先の選択肢に違いあり
大学と専門学校の就職率はほぼ同じ水準ですが、就職の内容には大きな違いがあります。大学卒業生は、総合職や公務員、大手企業の管理職候補として採用されるケースが多いのに対し、専門学校卒業生は特定の職種に直結した就職が中心になります。例えば、看護や美容、調理などの分野では、専門学校で学んだスキルがそのまま仕事に活かされるため、就職率が高い傾向にあります。
一方で、大学卒業者の方が選べる職種や業界の幅が広いのも事実です。特に、金融や商社、コンサルティング業界などでは、学歴を重視する企業が多く、専門学校卒業生は応募すらできないケースがあります。希望する職種や業界によっては、専門学校よりも大学の方が有利になる場合もあるため、事前に業界研究をしておくことが大切です。
2-3. 分野別ではこう違う!就職率が高い分野・低い分野
専門学校の就職率は、分野によって大きく異なります。例えば、看護・福祉・医療系の専門学校は資格取得が前提となるため、就職率がほぼ100%に近い傾向があります。一方で、デザインや音楽、ファッション系の専門学校は競争が激しく、全員が希望の職に就けるわけではありません。
ITやエンジニアリング系は、スキルがあれば専門学校卒でも企業から評価されやすく、高い就職率を誇ります。しかし、プログラミングやネットワーク技術など、実践的なスキルを磨いておかないと就職が難しくなることもあります。専門学校を選ぶ際は、その分野の就職率や求人数、卒業生の進路などをしっかり確認することが重要です。
2-4. 東京など都市部と地方ではどう違う?地域による就職率格差
都市部と地方では、専門学校卒業生の就職状況に違いがあります。東京や大阪などの大都市では企業数が多いため、求人の選択肢も豊富です。特にITやクリエイティブ業界では、都市部の方が圧倒的にチャンスが多く、専門学校の就職率も高くなります。
一方、地方では求人の数が限られるため、地元企業への就職が中心になります。しかし、地方の専門学校は地元企業と強いパイプを持っていることが多く、地域に密着した就職サポートを受けられる利点もあります。都市部で就職を目指す場合と、地元での就職を希望する場合では、戦略が異なるため、自分のキャリアプランに合った学校選びが重要になります。
3. 「就職率○○%」だけに惑わされない専門学校の選び方

専門学校のパンフレットやウェブサイトでは、就職率の高さが強調されています。しかし、その数値だけで学校を選ぶと、希望する業界に就職できない可能性があります。就職率を見る際の注意点や、実際に就職に強い専門学校の見極め方を解説します。
3-1. 数字の裏を見る!志望業界への“業界就職率”をチェックしよう
専門学校を選ぶ際、最も重要なのは「業界就職率」です。就職率○○%と書かれていても、その中にアルバイトや非正規雇用が含まれている場合があります。また、就職した業界が学んだ分野と無関係である可能性も考えられます。例えば、デザイン系の専門学校で「就職率90%」と記載されていても、そのうち何割がデザイン業界に就職したのかを確認しないと、実態が分かりません。
業界就職率を確認する方法はいくつかあります。まず、専門学校の公式サイトやパンフレットで「卒業生の進路一覧」をチェックしてください。具体的な企業名や職種が記載されているかどうかがポイントです。また、オープンキャンパスや説明会で「この学科の卒業生はどの業界に何割くらい就職しているか」と直接質問するのも有効です。曖昧な回答しか得られない場合は、就職実績に不安があるかもしれません。
3-2. 就職率の高い専門学校に共通する特徴とは?
就職に強い専門学校には共通する特徴があります。その一つが「業界との強い連携」です。企業との共同プロジェクトや講師に現役のプロを招く学校は、実務に直結する教育を提供しているため、卒業後の就職につながりやすくなります。さらに、インターンシップが充実している学校も強みになります。実際の職場で経験を積むことで、学生は即戦力として評価され、企業側も採用しやすくなるからです。
また、キャリアサポートが手厚い学校も就職率が高い傾向があります。例えば、履歴書やポートフォリオの添削、模擬面接、企業紹介など、個別対応が充実している学校は、内定獲得までの支援が手厚いため安心です。加えて、卒業生が業界で活躍している学校は、OB・OGのネットワークを通じて求人情報が回ってくるケースもあります。こうした学校は、実績がある分、企業からの信頼も厚く、毎年安定した就職率を維持できるのです。
3-3. 専門学校の情報公開資料を活用しよう
専門学校の就職実績を客観的に判断するには、情報公開資料を確認するのが有効です。文部科学省の「職業実践専門課程」に認定されている学校では、卒業生の進路や就職先の詳細なデータを公開することが義務付けられています。公式サイトの「情報公開」のページをチェックし、「就職者数」「進学者数」「業界別の就職割合」などのデータがあるかを確認しましょう。
さらに、高等教育無償化の対象校では、就職率や離職率なども公開されています。ここで「就職希望者ベースの就職率」だけでなく、「卒業生全体を分母とした就職率」も確認できれば、より実態に近いデータを把握できます。学校によっては、非正規雇用の割合や、卒業後1年以内の転職率なども公表している場合があるため、より詳細な情報を知りたい場合は、こうしたデータを活用するとよいでしょう。
4. IT業界が専門学校生におすすめな理由【東京で就職率が高い分野!】

専門学校卒業後の就職先として、IT業界は特におすすめの選択肢です。IT分野は常に人材不足が続いており、専門学校で学んだスキルを活かしやすい環境が整っています。ここでは、IT業界の魅力や専門卒でも活躍できる理由を解説します。
4-1. IT業界は人材不足!若手のチャンスが豊富な“売り手市場”
IT業界は深刻な人材不足に直面しており、特に若手エンジニアの需要が高まっています。デジタル化の加速により、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が進み、ソフトウェア開発やシステム運用の求人が急増しています。この背景から、未経験者や専門学校卒でも積極的に採用する企業が増えています。
例えば、クラウド技術やAI、データサイエンスの分野では、新卒でも基礎スキルを持っていれば育成前提で採用されるケースが多く見られます。専門学校で学んだ実践的なスキルをアピールできれば、企業の即戦力として期待されるでしょう。特に東京の企業では、新卒採用枠が多く、地方と比べて求人数が豊富です。IT業界に興味があるなら、積極的にチャレンジすべき分野です。
4-2. 学歴より実力主義!専門卒でも活躍できるIT業界の風土
IT業界は、他の業界と比較して学歴を重視しない企業が多いです。特にWeb系企業やスタートアップでは、「大学卒かどうか」よりも「何ができるか」が採用基準になります。プログラミングスキルやネットワークの知識があれば、専門学校卒でも十分に評価されるのが特徴です。
例えば、エンジニア採用では「実際にコードを書けるか」が重要視されるため、専門学校でプログラミングを学び、ポートフォリオを作成しておけば、学歴に関係なく採用される可能性が高まります。実際、多くのIT企業では、学歴よりも「GitHubの活動状況」「個人開発の経験」「資格取得」などを評価する傾向があります。専門学校卒だからといって不利になるわけではなく、むしろ実務に直結するスキルを身につけていれば、大学卒よりも即戦力として見られることが多いです。
4-3. 多彩な職種と高い給与水準、将来性も抜群のIT分野
IT業界には、さまざまな職種があり、自分の適性や興味に合わせてキャリアを選べます。プログラマー、システムエンジニア、ネットワークエンジニア、Webデザイナー、データサイエンティストなど、技術を活かせる職種が多数あります。また、未経験者向けの研修制度が整っている企業も多いため、専門学校卒でもスムーズにキャリアをスタートできます。
さらに、IT業界の給与水準は他業界と比べても高めです。エンジニアの初任給は、一般的な事務職や販売職よりも高く設定されていることが多く、経験を積むことで年収アップが期待できます。実力主義の業界なので、スキルが評価されれば若いうちから高収入を得ることも可能です。特に、フリーランスエンジニアや起業といったキャリアパスもあり、長期的な将来性も高いと言えます。
5. 専門学校生が希望の就職をつかむために今できる5つのこと

専門学校を卒業すれば自動的に就職できるわけではありません。希望する業界や職種に就くためには、在学中から戦略的に準備を進めることが重要です。ここでは、専門学校生が就職活動を成功させるために、今すぐできる5つの具体的なアクションを紹介します。
5-1. 在学中にインターンやアルバイトで“実務経験”を積もう
就職活動で企業から評価されるポイントの一つが「実務経験」です。専門学校で学んだ知識を活かし、実際の現場で経験を積んでおくことで、企業にとって魅力的な人材になれます。特にIT業界やデザイン業界では、ポートフォリオや実績が重視されるため、アルバイトやインターンシップを通じて実務スキルを高めることが有効です。
例えば、プログラマー志望であれば、エンジニアのアシスタント業務を行うアルバイトに就くことで、開発の流れを学べます。デザイナーを目指す場合は、デザイン事務所や広告代理店でのアルバイトを経験すると、実際の仕事の進め方を理解できます。こうした経験は、履歴書や面接でアピールできる材料となり、内定獲得の確率を高めます。
5-2. 資格取得で就職活動をさらに有利に【業界別おすすめ資格】
資格は、スキルを客観的に証明する手段として有効です。専門学校で学んだ知識を活かし、業界で評価される資格を取得すれば、採用の際にプラスに働きます。特にIT業界や医療・福祉系の職種では、資格が必須になることもあるため、早めの対策が必要です。
例えば、IT業界では「基本情報技術者試験」や「AWS認定資格」、デザイン業界では「Adobe認定エキスパート」、医療系では「医療事務技能認定試験」などが推奨されます。これらの資格を持っていると、企業からの評価が高まり、就職活動を有利に進められるでしょう。試験の難易度や勉強時間を考慮し、卒業までに取得可能な資格を選ぶことが重要です。
5-3. 学校の就職サポートをフル活用する
専門学校には、就職活動を支援するためのキャリアセンターや就職課が設置されています。これらのサポートを積極的に活用することで、求人情報の取得や面接対策がスムーズに進みます。特に専門学校では、企業とのコネクションを活かした「推薦枠」や「独自求人」があることが多いため、一般の就職活動よりも有利な条件で内定を獲得できる可能性があります。
履歴書やエントリーシートの添削、模擬面接、企業説明会の参加など、学校のサポートを最大限に活用することが重要です。授業やアルバイトが忙しくても、定期的に就職課に相談し、最新の情報を得るようにしましょう。早めの準備が、希望の就職先に内定するための鍵になります。
5-4. 企業のニーズを意識して必要なスキルを磨く
企業は、新卒採用の際に「即戦力」となる人材を求めています。そのため、採用されるためには、企業が求めるスキルを把握し、それに合わせた準備をすることが重要です。例えば、ITエンジニアを目指すなら「プログラミングスキル」、デザイン業界なら「PhotoshopやIllustratorの実務経験」、営業職なら「プレゼンテーション能力」など、業界ごとに求められるスキルは異なります。
企業の求めるスキルは、求人票や企業の採用ページに記載されていることが多いため、事前に調べておくとよいでしょう。また、業界のトレンドを知ることで、採用担当者に「成長意欲がある」と評価されやすくなります。業界研究をしながら、自分のスキルを高める努力を続けましょう。
5-5. (IT志望者向け)ポートフォリオで自分の実力を見せる
IT業界やクリエイティブ業界では、履歴書や面接だけでなく、「ポートフォリオ(作品集)」が重要な評価材料になります。特にプログラマーやデザイナーは、実際にどのようなスキルを持っているかを示すために、自分の制作物をまとめたポートフォリオを用意することが求められます。
プログラマー志望なら、GitHubに自分のコードを公開し、開発したアプリやシステムの紹介ページを作成するとよいでしょう。デザイナーなら、過去の作品をオンラインポートフォリオとして整理し、面接で実際に見せられる形にすると効果的です。こうした取り組みは、企業に対してスキルの証明となるだけでなく、「自主的に学び、成長する姿勢」をアピールする材料にもなります。
6. まとめ:専門学校の就職率を正しく理解し、自分のキャリアに活かそう
専門学校の就職率は高いとされますが、その数値には計算方法の違いや業界ごとの差があるため、表面の数字だけで判断するのは危険です。就職率の高さに惑わされず、「業界就職率」や卒業生の進路を確認することが重要です。
特にIT業界は、専門学校生にとって魅力的な選択肢です。人材不足による高い需要、学歴に左右されにくい評価基準、多様な職種と高収入の可能性があるため、スキルを身につければ有望なキャリアを築けます。
就職を成功させるには、在学中からインターンやアルバイトで実務経験を積み、資格取得やポートフォリオの充実を図ることが欠かせません。また、学校のキャリアサポートを活用し、企業の求めるスキルを意識しながら準備を進めることで、希望の職に就く確率を高められます。
専門学校の就職率を正しく理解し、戦略的に動くことが、理想のキャリアを実現するための鍵です。情報収集と実践を積み重ね、納得のいく就職を目指しましょう。
