専門学校生のインターンシップ完全ガイド~始める時期・探し方・給料まで徹底解説~
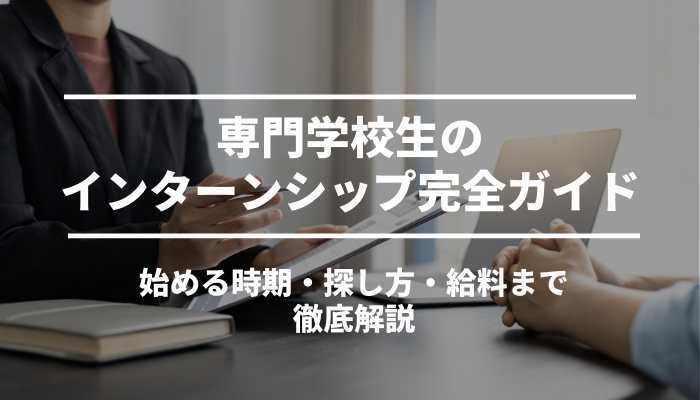
専門学校の在学中にインターンシップに参加すべきか悩んでいませんか?
「いつから始めればいいのか分からない」「そもそも専門学生も応募できるのか不安」と感じている方も多いはずです。
限られた在学期間の中で、何を優先して行動すればいいのか迷ってしまいますよね。
本記事では、専門学校生がインターンに参加するメリットや適切な時期、探し方、注意点までをわかりやすく解説します。
特にIT業界を例に挙げながら、実践経験を積む価値や就職にどうつながるのかをPREP形式で丁寧にお伝えしていきます。
この記事を読めば、インターンに参加すべき理由と具体的な行動の流れが理解でき、将来に向けて自信を持って一歩踏み出せるようになります。
ぜひ最後まで読み進めて、あなたの進路に活かしてください。
1.専門学校生にインターンシップは必要?まず知っておきたい基礎知識

専門学校生がインターンシップに参加する意義を理解することは、今後の進路や就職活動に大きく関わります。ここでは、専門学校の「実習」と「インターンシップ」の違いや、大学生との違いを踏まえながら、インターン参加のハードルや可能性について詳しく解説します。
1-1.専門学校の「実習」と「インターンシップ」の違いとは
専門学校における「実習」と「インターンシップ」は、似ているようで異なる制度です。
実習は学校のカリキュラムの一環として行われ、原則として無給であり、単位認定が前提になります。
一方で、インターンシップは企業が独自に実施する就業体験プログラムで、報酬が発生することもあり、参加期間や内容も多様です。
つまり、実習は学校が管理する学習の延長であり、インターンシップは就職活動を見据えた実践の場という位置づけになります。
両者の違いを理解することで、自分にとって何が必要かを判断しやすくなります。
1-2.専門学校生でもインターンに参加できる?大学生との違い
専門学校生でもインターンシップへの参加は可能です。
大学生を対象としたインターンが多い印象がありますが、専門学校生も歓迎している企業は存在します。
ただし、大学生に比べて在学期間が短いため、早めの行動が求められる点が大きな違いです。
また、応募条件に「大卒以上」と書かれている求人もあるため、事前確認が必要です。
早期に準備を始めれば、専門知識を活かせる職場での経験を積むことができます。
2.インターンシップはいつから始めるべき?【専門学校生の適切なタイミング】

専門学校生にとって、インターンシップに参加する時期は非常に重要です。ここでは、就職活動との関係を踏まえた最適な開始時期や、学年別に考えるタイミングの違いについて解説します。
2-1.就活スケジュールから逆算するベストな開始時期
インターンシップは就職活動の準備として、早めに始めるのが理想です。
理由は、専門学校生の就活は大学生よりも短期間で進行するため、インターンの経験を積む時間が限られているからです。
例えば、2年制の専門学校では2年次の夏から企業説明会や選考が本格化するため、それ以前の1年次後半にインターンを経験しておくと、就職活動で有利になります。
このように、就活スケジュールを逆算して動くことで、準備不足による焦りを防げます。
2-2.専門学校の種類別・学年別の違い(1年制・2年制・4年制)
インターンに参加するタイミングは、専門学校の在学年数によって異なります。
なぜなら、1年制・2年制・4年制では就職活動までの猶予が大きく異なるためです。
1年制では入学直後から情報収集を始めないと、インターンに参加する時間が取れません。2年制では1年次後半、4年制であれば2〜3年次が実践的な経験を積むタイミングとして適しています。
このように、自分の課程に合ったスケジュールを立てることが、就職に向けて着実なステップを踏むために欠かせません。
3.インターン先の探し方・見つけ方【学校紹介と自主応募】

インターンシップに参加したいと考えても、どのように探せばよいか悩む人は多いです。この章では、専門学校生が活用できる主な探し方として、学校からの紹介と自分での応募方法、さらに応募先を見極めるポイントについて解説します。
3-1.学校経由で探す方法 – キャリアセンターや講師の紹介
インターンシップを探す方法として、学校のキャリアセンターや担任の先生に相談することは非常に効果的です。
なぜなら、学校側は企業と連携しており、信頼できる紹介先を持っているケースが多いためです。
たとえば、過去に卒業生がインターンや就職をした企業を紹介してもらえることがあり、安心して応募できます。
このように、学校を通じて探すことで、ミスマッチのリスクを抑えながらスムーズに参加先を決めることができます。
3-2.自分で応募する方法 – 求人サイト・企業に直接アプローチ
学校以外で探すなら、自分で求人サイトを使ったり企業に直接問い合わせる方法もあります。
理由は、学校の紹介枠だけでは選択肢が限られる場合が多いためです。
たとえば、「専門学生歓迎」の条件で絞れる求人サイトや、企業の採用ページから直接応募するケースが増えています。
このように、主体的に行動することで、希望に合ったインターン先に出会える可能性が広がります。
3-3.専門学校生歓迎のインターンを見分けるポイント
インターンを選ぶ際は、自分が応募可能かどうかをしっかり見極めることが大切です。
なぜなら、大学生のみを対象にしたインターンも多く、専門学生は応募対象外となるケースもあるからです。
応募要項に「学歴不問」「専門学生可」などの記載があるかを確認し、不明な点は直接問い合わせて確認すると確実です。
このように、事前に確認を怠らなければ、無駄なエントリーを避けて効率よくインターンを探すことができます。
4.インターンシップに参加するメリット【専門学校生が得られるもの】

インターンシップに参加することで得られるメリットは多岐にわたります。ここでは、就職活動や将来のキャリア形成において特に役立つ4つの観点から、専門学校生にとっての価値を明確にしていきます。
4-1.就職活動でのアピール材料になる
インターンシップ経験は、就職活動での重要なアピール要素になります。
なぜなら、実務を体験したことがある学生は、職場でのイメージが明確であり、企業にとって即戦力と感じてもらいやすいからです。
たとえば、インターン先で担当した業務や学んだことを面接で具体的に話せれば、自己PRに説得力が増します。
このように、インターン経験があることで、他の応募者と差をつけやすくなります。
4-2.業界や職種の理解が深まる
実際の現場を経験することで、業界や職種への理解が大きく深まります。
理由は、教室で学ぶ知識と現場で求められるスキルにはギャップがあり、それを実感できるからです。
たとえば、IT業界に興味がある場合、現場の雰囲気や業務の進め方を実際に知ることで、自分に向いているかどうか判断できます。
このように、インターンは職業選択に迷っている人にとって、大きな判断材料になります。
4-3.人脈やコネクションが得られる
インターンでは、将来に繋がる人脈を築くことができます。
なぜなら、現場で一緒に働く社員や他のインターン生との交流が、就職活動にも活きるからです。
たとえば、インターン先の社員から就活時にアドバイスをもらえたり、紹介によって次のチャンスが広がるケースもあります。
このように、インターンで築いた人間関係は、キャリアにおける貴重な財産になります。
4-4.社会人としての基礎力が身につく
インターンは、社会人として必要な基礎力を実践的に学べる場でもあります。
理由は、時間管理や報連相、チームでの連携など、学校では学びにくい要素を経験できるからです。
たとえば、業務の報告やメール対応などのビジネスマナーを身につけることで、入社後のギャップを軽減できます。
このように、社会人としての土台を早期に築けることは、就職後の安定したスタートに繋がります。
5.インターンシップのデメリット・注意点【参加前に知っておこう】

インターンシップには多くのメリットがありますが、注意点も存在します。ここでは、専門学校生がインターンに参加する前に把握しておくべき4つのリスクについて解説します。事前に知っておくことで、後悔のない選択ができるようになります。
5-1.学業との両立が難しい場合がある
インターンシップと学業の両立が困難になることがあります。
なぜなら、専門学校はカリキュラムが詰まっているため、授業や課題とインターンの日程が重なることが多いからです。
たとえば、試験前に長時間のインターンが入ると、成績に影響することもあります。
このように、無理にスケジュールを詰め込むと本末転倒になるため、参加前に学校の予定をしっかり確認することが重要です。
5-2.希望業界以外での経験は評価されにくい
インターン先が希望業界と異なる場合、就職活動でのアピールにつながりにくいです。
その理由は、経験と志望動機の一貫性が薄れてしまうと、企業側に「なぜこの業界を志望するのか」という説得力を持たせにくくなるからです。
たとえば、医療系の専門学校に通っていながら、アパレル業界でインターンを行った場合、就職活動で評価されにくくなります。
このように、インターンの目的と進路を結びつける意識を持つことで、就職活動で活きる経験になります。
5-3.インターン募集が少なく競争が激しい
専門学校生向けのインターンシップは、大学生向けと比べて選択肢が少ない傾向にあります。
なぜなら、インターン募集の多くが「大学生以上」を対象としているため、専門学生が応募できる機会が限られているからです。
たとえば、インターン求人サイトで検索しても、条件に合うものがなかなか見つからないと感じることがあります。
このような現状を理解した上で、早めに情報収集を始めることが、チャンスを逃さないために必要です。
5-4.(有給の場合)待遇や労働環境の確認が必要
有給インターンに参加する際は、条件や労働環境を事前に確認する必要があります。
理由は、報酬が発生する場合でも、内容や労働時間が法的に不適切であるケースが稀に存在するためです。
たとえば、最低賃金を下回る報酬や、契約内容が曖昧なままの勤務はトラブルの原因になります。
このような問題を避けるためにも、応募前に契約内容や勤務条件をしっかり確認することが大切です。
6.インターンシップの給料は出る?有給インターンと無給インターンの実情

インターンシップに参加する際、多くの専門学校生が気になるのが「給料がもらえるかどうか」です。この章では、無給が基本とされる学校の実習と、給料が発生する有給インターンとの違い、そして参加時に確認すべきポイントについて解説します。
6-1.専門学校のカリキュラム実習は基本“無給”
専門学校の授業に組み込まれている実習では、原則として給料は支払われません。
その理由は、実習が「職業体験」の一環として扱われており、労働契約ではないためです。
たとえば、医療系や福祉系の専門学校では、提携先の施設で一定期間実務を学びますが、あくまで学習目的であり報酬は発生しません。
このように、学校のカリキュラムとして組まれている実習は、「働く」のではなく「学ぶ」ことを目的とした場になります。
6-2.長期インターンは“有給”が主流:その相場と支払い形態
一般企業が実施する長期インターンシップでは、給料が支払われるケースが増えています。
その背景には、業務内容が実践的で、学生に一定の労働力を求める企業が多いためです。
たとえば、ITベンチャーでは時給1,000〜1,500円程度の報酬が設定され、週3日程度の勤務で月5万円以上を得る学生もいます。
このように、有給インターンは収入だけでなくスキルアップも見込める貴重な経験となります。
6-3.有給インターンに参加する際のチェックポイント
有給インターンに参加する際は、条件を十分に確認することが重要です。
なぜなら、報酬が出るからといって、必ずしも適正な労働環境が整っているとは限らないからです。
たとえば、成果報酬制で実質的に収入が得られない内容だったり、業務時間が過度に長くなると学業に支障が出る可能性があります。
このようなリスクを避けるためには、契約書や勤務条件を事前に確認し、納得できる環境で働くことが大切です。
7.インターン先の業界はどう選ぶ?専門分野を活かす or 未経験分野に挑戦

インターン先の業界選びは、将来の進路や就職活動に直結する重要な判断です。この章では、自分の専門分野を活かす選択と、あえて未知の分野に挑戦するケースの両方に触れながら、それぞれの特徴や注意点を解説します。さらに、業界ごとのインターン傾向についても紹介します。
7-1.専門分野を活かせる業界で経験値アップ
インターン先を選ぶ際は、まず自分の専門分野に関連した業界を優先するのが理想です。
その理由は、すでに学んでいる知識やスキルを現場で発揮しやすく、企業からも即戦力として期待されやすいためです。
たとえば、IT系の専門学校に通う学生が開発会社でインターンを行えば、実践の中で自分の力を試せる機会になります。
このように、自分の専門を活かせる環境で経験を積むことで、将来のキャリアに直結する強みが得られます。
7-2.あえて他業界を体験するメリットと注意点
インターン先として、あえて専門外の業界を選ぶことで得られる学びもあります。
なぜなら、異なる環境での経験は自分の視野を広げ、新たな可能性を見出すきっかけになるからです。
たとえば、デザイン系の専門学校に通う学生が営業職のインターンに参加した場合、コミュニケーション力や提案力といった汎用的なスキルが身につきます。
このように、異業種での経験は自己理解を深める機会になりますが、就職活動での一貫性を保つためには志望理由の整理も必要です。
7-3.業界ごとのインターン傾向:人気のIT・クリエイティブ系は?
インターンにおける業界ごとの傾向を理解しておくと、応募時のミスマッチを減らせます。
その理由は、業界によってインターンの受け入れ体制や求められるスキル、期間の長さなどが大きく異なるためです。
たとえば、IT業界やWeb制作業界では長期インターンを積極的に受け入れており、専門学校生歓迎の案件も豊富にあります。一方、医療や保育などの分野では、実習中心でインターン募集自体が少ない傾向です。
このように、自分の進みたい業界がどのようなインターンを行っているのかを事前に調べることで、応募の戦略が立てやすくなります。
8.まとめ:専門学校生のインターンシップで将来の選択肢を広げよう
専門学校生にとって、インターンシップは将来の可能性を広げるための大きなチャンスです。実習とは異なり、インターンは実際の企業の中で働きながら経験を積める貴重な機会となります。特に就職活動を見据えた準備として、早めに参加しておくことが内定獲得の近道にもなります。
インターンを通じて、専門分野のスキルを磨いたり、業界への理解を深めたりすることができます。また、自分に合った職場の雰囲気を知るきっかけにもなり、キャリア選択の精度を高められます。さらに、有給インターンであれば収入も得られ、実践力と経済的メリットの両方を得られるのも魅力です。
一方で、参加時期の見極めや、学業との両立、労働環境の確認など、事前に把握すべき注意点も存在します。しかし、それらを正しく理解し、適切な準備をして挑めば、インターンは専門学校生にとって非常に有意義な経験になります。
今後の進路をより確かなものにするために、インターンシップへの第一歩をぜひ踏み出してみてください。行動することで、あなたの選択肢は確実に広がります。
