専門学校の履歴書はこう書く!学歴・志望動機の正しい記載例
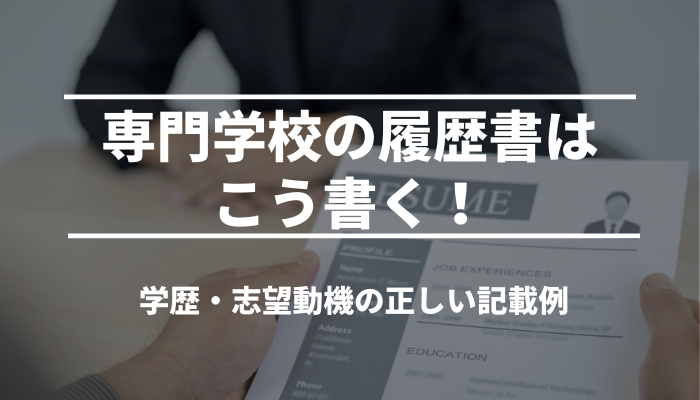
専門学校を卒業した場合、履歴書にはどう書けばいいのか悩んでいませんか?
「どこまで書くのが正解なのか」「専門学校は本当に学歴として通用するのか」と不安に感じている方は多いはずです。
記載方法を間違えてしまうと、採用担当者に誤解を与えたり、不利な印象を持たれたりする可能性もありますよね。
本記事では、履歴書における専門学校の正しい書き方や、ケース別の記載例、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
さらに、専門学校卒業を強みに変えるための考え方や、IT業界のようにスキル重視の業界で有利になる理由についてもご紹介します。
この記事を読むことで、履歴書に何をどう書けばいいかが明確になり、就職活動に自信を持って取り組めるようになります。
専門学校での経験を正しく伝え、採用担当者に好印象を与える第一歩を踏み出しましょう。
1.専門学校は履歴書に学歴として書けるのか
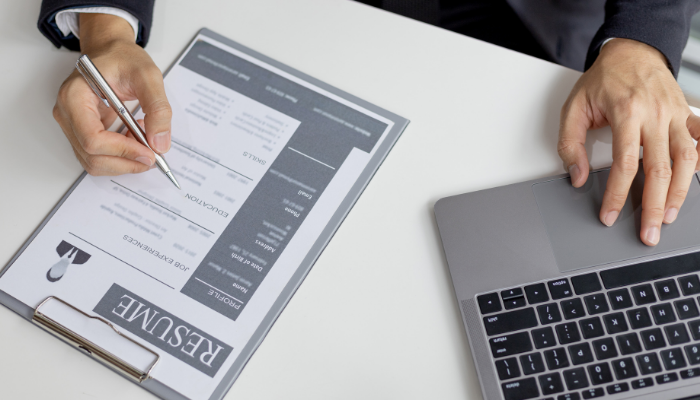
専門学校が履歴書に学歴として書けるかどうかは、就活を始める多くの学生が最初に抱く疑問です。この章では、学歴と認められる専門学校の条件や、そもそも専門学校卒が就職活動においてどのように評価されるかを解説します。次の見出しでは、認可校と無認可校の違いや、最終学歴の考え方について詳しく触れていきます。
1-1.専門学校は学歴欄に記載できる
専門学校は、国や都道府県から認可された教育機関であれば、学歴欄に記載できます。なぜなら、認可校は「学校教育法」に基づき、一定の教育課程や修業年限が定められているためです。例えば「学校法人〇〇学園〇〇専門学校」のように正式な名称で記載されていれば、企業側も正規の学歴と認識できます。そのため、認可された専門学校に通っている、あるいは卒業した場合は、堂々と学歴として履歴書に書きましょう。
1-2.無認可の専門校やスクールは学歴に含まれない
スクールやカルチャー教室などの無認可校は、学歴に含まれません。なぜなら、これらの教育機関は「専門学校」という名称を使用していても、正式な学歴を授与する権限がないからです。たとえば、資格取得を目的とした民間スクールの場合、学歴欄ではなく資格欄や自己PR欄でアピールするのが適切です。無認可校を学歴として記載してしまうと、経歴詐称と誤解されるおそれもあるため、注意が必要です。
1-3.最終学歴は通った順番ではなく教育水準で決まる
最終学歴は、最後に通った学校ではなく、最も高い教育課程を修了した学校で判断されます。これは、採用担当者が学歴を評価する際に教育水準を基準にしているからです。たとえば、大学卒業後に専門学校に通った場合、最終学歴は「大学卒」となります。逆に高校卒業後すぐに専門学校を修了した場合は、「専門学校卒」が最終学歴です。このように、履歴書を記載する際は、自身の最終学歴を正しく認識することが大切です。
2.履歴書に専門学校を書くときの基本ルール

専門学校を履歴書に記載する際は、学歴欄に正確かつ丁寧に記入する必要があります。誤解を招かず、採用担当者に良い印象を与えるためにも、いくつかの基本的なルールを押さえておきましょう。ここでは、記入の順番や書き方のポイント、正式名称の使い方など、正確に伝えるために必要なルールについて詳しく解説します。
2-1.履歴書の学歴欄は高校卒業から記載する
履歴書の学歴欄は、高校卒業から書き始めるのが基本です。なぜなら、義務教育は中学校までであり、学歴として区別されるのは高等学校以降だからです。仮に中学から記載してしまうと、採用担当者に違和感を与える可能性があります。また、高校名は「〇〇高等学校」と正式名称で書き、入学と卒業をそれぞれ別の行に記載することが求められます。このように記載ルールを守ることで、丁寧な印象を与えることができます。
2-2.学科やコースまで正式名称で記載する
専門学校名を書く際は、学校法人名や学科、コース名までを略さず正式名称で記載してください。正式名称を使う理由は、採用担当者が教育内容や取得資格を正確に把握できるようにするためです。たとえば、「学校法人〇〇学園 〇〇専門学校 情報処理科 システムエンジニアコース」といったように書くと、学んだ内容が明確になります。簡略化せずに書くことが、信頼性を高めるポイントです。
2-3.西暦と和暦は混在させず統一する
履歴書では、西暦と和暦のどちらを使っても問題ありませんが、必ずどちらかに統一しましょう。混在してしまうと、採用担当者に対して不注意な印象を与える可能性があるからです。たとえば、西暦で記載する場合は「2023年4月入学」、和暦なら「令和5年4月入学」とすべて同じ形式に揃えます。細かな部分ではありますが、統一感のある履歴書は読み手に誠実な印象を与えます。
2-4.学歴欄の最後には「以上」と書いて締める
学歴欄の末尾には、必ず「以上」と書いて締めくくりましょう。これは、記載が完了していることを示すための決まりです。なぜ「以上」が必要かというと、記入漏れや記載忘れがないことを相手に明確に伝える役割を持っているからです。実際、「以上」の一言があるだけで、履歴書全体の完成度が高く見える効果もあります。採用担当者に安心感を与えるためにも、最後まで丁寧に仕上げましょう。
3.ケース別 専門学校の履歴書の書き方

専門学校に通っていた期間の状況によって、履歴書に記載する方法は少しずつ異なります。たとえば、在学中か卒業見込みか、あるいは中退しているかなど、記載の表現を正しく選ぶことが求められます。この章では、それぞれのケースごとに正しい記載例と注意点を解説します。
3-1.在学中や卒業見込みの場合
専門学校に在学中、または卒業見込みの場合は、卒業予定年月と「卒業見込み」の表記を使って記載します。このように書く理由は、採用担当者に学歴の進行状況を正確に伝えるためです。たとえば、「2025年3月 専門学校〇〇学科 卒業見込み」と明記すれば、在学中であることと卒業の見通しがあることが一目でわかります。曖昧な表現は避けて、明確な情報を記載することが信頼につながります。
3-2.既に卒業している場合
卒業済みである場合は、入学年月と卒業年月の両方を記載してください。こうすることで、学習期間と在籍状況が明確になります。たとえば「2021年4月 専門学校〇〇学科 入学」「2023年3月 専門学校〇〇学科 卒業」と記載すると、2年間の課程を修了したことが伝わります。入学と卒業をそれぞれ別の行で記載するのが正式なルールであり、読み手の混乱を防ぐためにも重要です。
3-3.中退した場合
中退した場合は、「中途退学」と記載し、必要に応じて理由も補足します。中退を明記する理由は、空白期間を作らず経歴を正直に示すことで、不信感を与えないためです。たとえば「2022年4月 専門学校〇〇学科 入学」「2023年3月 専門学校〇〇学科 中途退学」と書くことで、在籍していた事実と時期が明確になります。中退理由は「一身上の都合」などの表現で差し支えありません。
3-4.休学や復学の経歴がある場合
休学や復学の経験がある場合は、その旨を簡潔に記載しましょう。記載する目的は、空白期間の説明責任を果たすことで、履歴書全体の整合性を保つためです。たとえば「2022年4月 専門学校〇〇学科 入学」「2023年4月~2023年9月 休学(体調不良のため)」「2023年10月 復学」と記載すれば、一時的な離脱とその理由が伝わります。復学して卒業した場合は、最後に卒業年月も忘れずに記載しましょう。
3-5.学科変更や転校をした場合
学科変更や転校をした場合は、それぞれの入学・変更・卒業の経緯を時系列で記載します。このようにすることで、学び直しや進路変更の意図が自然に伝わるからです。たとえば「2021年4月 専門学校〇〇学科 入学」「2022年4月 同校△△学科に変更」「2023年3月 △△学科 卒業」と記載することで、学科変更の経緯が明確になります。転校の場合も、旧校と新校の両方を記載しましょう。
4.履歴書に書けない専門学校とは

すべての「専門学校」が履歴書に学歴として書けるわけではありません。特に、学校名に「専門学校」と含まれていても、無認可の民間スクールである可能性もあるため注意が必要です。この章では、履歴書に記載できない専門学校の特徴や、記載方法に迷ったときの対応策について解説します。
4-1.無認可のスクールは学歴に該当しない
国や都道府県に認可されていないスクールは、たとえ「専門学校」の名称を使っていても学歴には該当しません。その理由は、学歴として認められるには、一定の教育課程や設置基準を満たしている必要があるためです。たとえば、資格取得や趣味の講座を目的としたスクールは教育機関ではないため、履歴書の学歴欄に記載すると誤解を招く恐れがあります。こうした場合は、資格欄や自己PR欄で補足しましょう。
4-2.学歴として書けるのは認可された専門学校のみ
履歴書に学歴として書けるのは、学校教育法に基づいて都道府県知事の認可を受けた専門学校に限られます。これは、認可校であることが教育の質や信頼性を保証する基準になっているからです。たとえば、文部科学省の認可を受けた「専修学校専門課程」は正式な学歴とみなされます。自分の通った学校が該当するか不安な場合は、在籍していた学校に問い合わせて確認するのが確実です。
4-3.迷ったときは学校名で判断せず学校法人かどうかを確認する
履歴書に書けるかどうかを判断する際、学校名に「専門学校」とあるかどうかではなく、その運営母体が「学校法人」かどうかで判断しましょう。なぜなら、名称だけでは認可の有無を判断できないためです。たとえば、株式会社が運営している教育施設は、たとえ名称が立派でも学歴としては扱われません。一方で、「学校法人〇〇学園」と明記されていれば、認可校である可能性が高いです。確実を期すには、学校案内や公式サイトで法人名を確認するのが良いでしょう。
5.専門学校卒が就職で不利にならないためにできること

専門学校卒業は立派な学歴であるものの、就職活動の場面によっては大卒と比較されて不利に感じることもあります。しかし、就職で評価されるのは学歴だけではありません。この章では、専門学校卒の強みを活かして就職活動で不利にならないために意識すべきポイントを解説します。
5-1.専門学校で学んだ専門性を明確に伝える
就職で不利にならないためには、専門学校で身につけたスキルや知識を具体的に伝えることが重要です。専門学校は実践的な教育が中心であり、即戦力としての能力をアピールできる点が強みです。たとえば、情報処理技術者試験の合格やプログラミングスキルの習得など、学んだ内容が職種と結びついている場合は大きな武器になります。採用担当者は実務に活かせる力を求めているため、学歴ではなく「何を学んだか」を伝えることが差別化につながります。
5-2.履歴書以外の自己PR欄で熱意をアピールする
履歴書の学歴欄だけでは伝えきれない内容は、自己PR欄を使って積極的にアピールしましょう。なぜなら、企業は学歴よりも人柄や意欲を重視する傾向があるからです。専門学校で努力した経験や、自主的に取り組んだ課外活動などを具体的に書くことで、熱意と行動力を伝えられます。自己PRをしっかり作り込むことで、学歴にとらわれず自分の価値を相手に届けることができます。
5-3.IT業界など専門スキルが評価される業界を狙う
専門学校卒業者にとって、IT業界はスキルが重視されるため特におすすめの業界です。なぜなら、IT業界では実務能力やプログラミング経験が採用に直結するケースが多く、学歴の優劣があまり影響しないからです。たとえば、未経験でもポテンシャル採用を実施しているIT企業は多く、ポートフォリオや資格でスキルを証明できれば高い評価を得られます。専門性を活かせる業界を選ぶことで、自分の能力を最大限に発揮しやすくなります。
6.専門学校の履歴書に関するよくある質問

履歴書に専門学校をどう書くかについては、基本的なルールを押さえていても細かな疑問が残ることがあります。特に、卒業順序や記載位置、複数の学歴がある場合の扱いなど、判断に迷うポイントも少なくありません。この章では、専門学校に関する履歴書の記載でよくある質問とその答えをわかりやすく説明します。
6-1.大学卒業後に専門学校を出た場合の最終学歴はどちらか
大学卒業後に専門学校を修了した場合、最終学歴は大学卒になります。理由は、最終学歴は「最も高い教育課程を修了した学校」を指すためです。大学は学士という学位が授与される高等教育機関であり、専門学校はそれに比べて教育水準が低いため、たとえ専門学校の方が後に卒業していても大学の学歴が上位となります。このようなケースでは、履歴書には大学と専門学校の両方を時系列で記載し、最終学歴欄には大学を記載してください。
6-2.認可された専門学校か確認する方法はあるか
自分が通っている専門学校が認可されているかどうかを確認する方法はあります。具体的には、学校案内や公式ホームページを確認し、設置者が「学校法人」となっているかどうかを見ればわかります。また、「専修学校専門課程」と明記されているかも重要なポイントです。これらの記載があれば、履歴書の学歴欄に正式な学歴として記載して問題ありません。不明な場合は、学校の事務局に問い合わせれば確実です。
6-3.スクールで学んだことはどこに書けばよいか
認可されていないスクールで学んだ内容は、履歴書の学歴欄には書けませんが、資格欄や自己PR欄に記載することが可能です。このように記載する理由は、学歴としては認められなくても、習得したスキルや資格が採用においてプラス評価につながる可能性があるためです。たとえば、「〇〇スクールにてWebデザインを1年間学習」「Photoshop®クリエイター能力認定試験合格」といったように具体的に記載することで、学んだ実績を有効にアピールできます。
7.まとめ
専門学校を履歴書に記載する際は、まずその学校が認可された教育機関であるかどうかを確認することが大切です。認可校であれば、正式な学歴として履歴書の学歴欄に記載できます。一方で、資格スクールなど無認可の機関は学歴としては書けず、別の項目でアピールする必要があります。
また、履歴書の学歴欄は高校卒業から記載し、学校名や学科・コース名を略さず正式名称で書くことが基本です。在学中、卒業見込み、中退、休学、学科変更など、ケースごとに適切な表現を使うことで、採用担当者に正しく伝わります。
専門学校卒という学歴は決して不利ではなく、学んだスキルや専門性を明確に伝えることで、むしろ大きな強みになります。特にIT業界のように実務能力が重視される業界では、専門学校での学びがそのまま評価につながる場面も多くあります。
履歴書は自分の経歴を伝える重要な書類です。形式的なルールを守るだけでなく、自分の学びや努力を正確かつ丁寧に伝えることで、採用の可能性を大きく広げることができます。専門学校での経験をしっかり言語化し、自信を持って就職活動に臨んでください。
